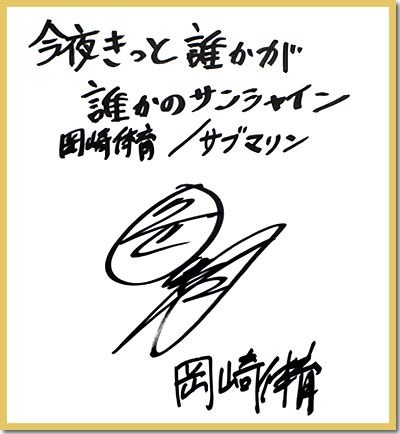その突き上げた拳に迷いはいらない的なこと
アブラカダブラ やかましい黙っとけ
フィジカル全振りMPは0 勢いで行け Be a Hero
みぞおち入ったら「ウッ」ってなるグーパンお見舞いもっと歌詞を見る
―― 人生でいちばん最初に歌詞を書いたのはいつ頃でしたか?
いちばん最初は…3歳のとき。作詞というか、日記を歌詞風に作るコンテンツが、僕の通っていた保育園でありまして。そのときに書いたのが<ありにすなかけたよ しんだよ>…この2行ですね。
初めて作詞作曲をしたのは中学2年生でした。「イエティ」というUMA(未確認動物)がテーマの曲で。イエティが人里に降りてきて、村の女性に恋をするんですけど、もしかしたら人間に危害を加えるかもしれないということで、射殺されるという。蟻が死んだり、イエティが死んだり、最終的に命を失ってしまいがちです。
―― ちなみに岡崎さんはどんな子ども時代だったのでしょう。
すごく目立ちたがり屋な部分と、引っ込み思案な部分が共存しているちょっと複雑な性格だったかもしれません。自信がないんだけど、シングルマザーのひとりっ子で育ったから、自己顕示欲も強くて。いつも自分を見ていてほしい、誰かに相手してほしいと思っていた気がします。
―― その気持ちが音楽づくりの初期衝動に繋がっていたのかもしれませんね。
まさにそうです。家に帰ってから遊ぶ兄弟もいないから、曲を作って母親に聴いてもらって、「すごいなぁ、こんなんできたんやなぁ」って評価してもらうのが嬉しい。そのサイクルがモノづくりをして他者に認められる、評価される喜びの原体験でした。
あと、母親の親戚がバンドを組んでいて、幼い頃から音楽に対して寛容な環境だったのも大きいですね。小学生のときには、お盆休みに親戚の家に遊びに行って、お兄ちゃんのギターや電子ドラムを触らせてもらったり。母親も音楽好きなので、すぐに楽器を買い与えてくれて。そうやって自然と音楽の道へ進んでいった気がします。
―― 岡崎さんも学生時代にバンドを組まれていたそうが、そこでも歌詞は書かれていましたか?
書いていました。ただ、あれを歌詞と言っていいのか…。たとえば、『ジョジョの奇妙な冒険』に出てくるブローノ・ブチャラティというキャラクターがいるんですけど、作中で彼が言っているセリフをエキサイト翻訳で英訳しただけの歌詞とか。曲タイトルは「ブローノ・ブチャラティ」。
―― でもそのままバンドでプロの道へ…とはならなかったのですね。

僕としてはバンドでやっていきたかったんですよ。当時はロックバンドが主流だったし、単純に好きですし、みんなでメジャーデビューしてみたかった。でもいかんせん僕の協調性がなくてですね…。うまくバンドをまとめて引っ張っていくことができなかったので、どんどんメンバーが脱退して、最終的に僕ひとりだけ残って。それでも音楽活動を続けたいなと思ったので、ひとりでやっていく岡崎体育というスタイルにたどり着きました。
―― アーティストとして“岡崎体育”という個性ができあがったと実感されたタイミングはありますか?
自分の音楽スタイルが明確に形になったと思ったのは、実は楽曲提供のタイミングでした。たとえば曲を書かせていただいたアイドルのファンの方々が、「めちゃくちゃ岡崎体育節!」ってSNSに書いてくれたりして。そのとき初めて、「俺にも節があったのか!」って気づかせてもらったというか。それは自分のなかだけでやっていたらわからない感覚でした。改めて自分の癖とかを理解することになった機会でしたね。
―― 今作にも提供曲である「休みの日くらい休ませて」と「Liar」のセルフカバーが収録されていますね。提供曲を書く際、何をいちばん大切にされますか?
そのアーティストがその曲をライブでやってくれることをイメージしながら書くことですね。たとえば「Liar」は、メンバーの方々がフレーズを1行ずつ歌ってくださる姿を想像しました。あまりブレスの位置を意識してない、ひとりの肺活量ではなかなか歌えない曲。メンバーが複数人いるからこそ成り立つ曲。だからセルフカバーしたときめっちゃ息継ぎしんどかった…(笑)。
「休みの日くらい休ませて」もライブで盛り上がったというお話を聞いて嬉しかったです。ちなみにこの曲は細かいオーダーがなく、「岡崎体育さんらしい曲でお願いします」と言っていただいたので本当に自由に作ったんですけど、アルバムの並びで聴いてみるとまぁ僕の曲が浮いていること。それでもファンの方が「岡崎体育の曲いい!」と言ってくれていたので、大きな達成感を得ることができたお仕事ですね。
―― 岡崎さんはかつて「レシピを英語風に読んだネタ」ツイートも話題になりました。そうした音としての言葉のコントロール力も“岡崎体育”楽曲にとっての大きな武器ではないでしょうか。
たしかに歌詞を音で捉えることのほうが多いかもしれないです。それも外国のバンドが好きだった母親の影響が大きいですね。僕も幼少の頃からQUEENとかをよく聴いていて。なんて歌っているかわからなかったから、何回も何回も聴いて、英語をカタカナに書き直して自分で歌えるようにして。それを繰り返していくうちに、「英語風の発音ってこんな感じやんな~」って感覚が培われて、大まかなルールや原理を掴んでいった気がします。
あと子どもながらに、音符に対する言葉のつき方も意識していたかもしれません。小学校の音楽で習う歌は大体、音符ひとつにひらがなひとつじゃないですか。でも外国の歌はそうじゃなくて。たとえば音符ひとつに「I Feel」ってカタカナ4文字分が入っていたりする。じゃあ音に対してどう言葉を流し込めば違和感なく聴こえるのか、そういうところを考えながら音楽を聴いていた経験が、僕の作詞の礎になっているんだと思います。
―― また、ある記事で「さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ (2019年)を終えたら引退する予定だった」とおっしゃっていたのを拝見しました。もともとそこで“岡崎体育”を完成させる計画だったのですか?
そうなんですよ。小学校の卒業文集にも書いていたんですけど、「作曲家になって世界中のひとに曲を聴いてもらいたい」というのが僕の原点の夢で。そのためにはまず自分自身を多くのひとの目にとめてもらうことが大事だなと思って、岡崎体育という活動を始めた。そして大きな目標を達成したらステージパフォーマンスは終わりにして、そこまで培ってきた人脈や経験を使って、思い描いていた作曲家活動をしようと考えていたんです。
でも想像以上に、岡崎体育という活動のなかでは楽しいことがたくさんあって。人前で歌って、これだけ拍手と声援をもらえて、こんなに自分を肯定できる仕事はないなと思ったんですよ。そういう気持ちがありながらここで急に身を引くのは、応援してきてくれた方々にもここまで育ててくれたレコード会社にも失礼だなと。それで、自分ができる限りは人前に立って活動し続けようと思い直しましたね。
―― 岡崎さんは常に「27歳の夏までにメジャーデビュー」「30歳までにさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ」など具体的な目標を立ててこられましたが、今のマインドはいかがでしょうか。
「さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ成功」までがすごく大変な道のりでしたし、自分のキャリアハイといっても過言でないほど僕の人生の誇りで。正直、もういつ死んでもいいと思えるぐらいなんです。なので、これからは本来の夢に沿って、「とにかく音楽を楽しみながら活動を続けていく」というふうにマインドシフトしていきたいと思っています。今まで以上に音楽を好きになって、音楽と一緒に楽しく生活していきたい。
でも強いて言えば、「ひとつのアルバムで10万枚セールスする」という夢はあって。やっぱりサブスクやYouTubeで音楽を聴くのが当たり前な時代になってきて、なかなか難しいことなんですけど。それでも諦めずに、フィジカルでもCDを買いたくなるような音楽を作るアーティストを目指して頑張っていますね。