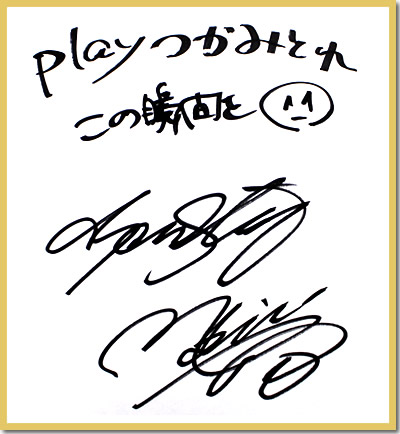忘れたころに 風のむこう 雲の先に 光るもっと 自由な汗 流そう もっと 自由な涙 流そう
言葉には できないような トキメキをいつもさがしている
Make it together!!La, la la …. 何があろうと La, la la …. あきらめないでもっと歌詞を見る
―― おふたりは人生で最初に音楽に心を動かされた記憶というと、何を思い出しますか?
堂珍 映画『スタンド・バイ・ミー』を観て、主題歌のベンE.キング「Stand By Me」を聴いたときですね。当時、ちょうど自分自身の年齢が主人公の少年と近かったし、重ねて観ていた部分もたくさんあった分、今でも強く印象に残っています。
川畑 僕は中学時代ですかね。4つ年上の兄がいるので、その影響でBOØWYとかZIGGYとかは聴いていたんです。そこから徐々に、「兄貴も聴いてないバンド、何かないかな?」っていろんなものを自分でも探し始めて、出会ったのがX JAPANでした。すぐにハマって、中学1年の頃、人生で初めてライブを観に行きました。
あと、当時はバンドブームで『BANDやろうぜ』という音楽雑誌もあって。兄はその雑誌でメンバーを探して、バンドを組んでいたんですよ。僕も歌は好きだったし、おもしろそうだなぁと。そして中学3年で、遊びではあるんですけど友だちとコピーバンドをやり始めました。
―― 学生時代、歌詞やポエムなどは書いていましたか?
川畑 そういう時期あったなぁ。何を書いていたかはまったく覚えてないんですけど(笑)。でも尾崎豊さんとか、THE BLUE HEARTSさんの歌詞が好きでよく読んでいました。わかりやすい言葉なのに突き刺さってきてアツい感じ。学生時代の自分とリンクするフレーズもたくさんあってより引き込まれたし。自分もそういう歌詞を書こうとしていた気がします。
堂珍 僕の場合はなくて。むしろ当時、「思いや考えを自分で言語化しなくて済む」と思ったのが音楽だったんですよね。だからオリジナルの歌詞を書くことを意識し始めたのは、オーディションのときぐらい。二十歳を超えてからでした。
―― テレビ番組『ASAYAN』の男子ボーカリストオーディションで選ばれたことが始まりであるCHEMISTRYですが、改めて振り返ってみると、おふたりの声の相性を当時はどのように感じていらっしゃったのでしょうか。
川畑 正直「化学反応」と言われても、まだそこまでの経験がなかったからピンと来なかったんです(笑)。だけど、まったく違うタイプの声なのに、どこか同じ成分を持っているような感覚がありました。そういう声の相性の良さは、活動していくなかでどんどん知っていったし、年々強く感じています。
堂珍 声を重ねたとき、気持ちよくてビリッ!っとすることがあって。僕はその感覚がいちばん最初からあったような気がします。
―― 『THE FIRST TAKE』で「You Go Your Way」や「My Gift to You」を聴いた際、それぞれのソロパートも素晴らしいのですが、おふたりの声が重なった瞬間、まさに「ビリッ!」という感覚を味わいました。
川畑 後輩のDa-iCE・大野雄大もそう言ってくれました。「ちょっと気持ち悪くなるぐらいだ」って(笑)。もう俺らとしては無意識だよね。
堂珍 うん。
川畑 オーディションのとき、「この人とは合わないかもしれないな」ってひともいましたし。単純に声だけじゃない、言葉ではうまく表せない、自分たちがそれぞれ持っているものが本能的に合う感覚があるんですよ。
堂珍 やっぱり声って感情とか想いを飛ばしているものだから。それが溶け合うかどうかって大事ですよね。「俺が俺が!」だと衝突するだけで。歌詞の解釈ひとつでも、「俺はこう思う」「そうか、そう思ったのか」ってキャッチボールしながら歌える。それは単純に性格の相性もあれば、「自分がこれまで何をやってきて、今ここに立って何を感じているか」の重なりでもあるんだと思います。
―― デビュー当時は、こんなに長くおふたりで活動される未来というのは想像されていましたか?
川畑 まったく想像してなかったですね。でも、早く終わるだろうなとも思ってなかった。自分の何かを変えたいから飛び込んだのがオーディションだったし、この先は自分たち次第だなと。なるようにしかならないなと。それは今でも思っています。でもまさかここまで長く続くとは…。本当に聴いてくれるひとがいるから、やり続けられている部分が大きいです。
堂珍 珍しいよね。オーディションスタートでこんなに続いているケースって。もう23年。
―― 生きてきた半分以上の年月を、CHEMISTRYとして過ごされているということですね。
川畑 そうなんですよ、実は。
堂珍 そうかぁ…。
川畑 みんな「20代は楽しかった!」って言うじゃないですか。俺らも楽しかったけど…とにかく「ケミ」だったんですよ(笑)。
―― 2012年~2017年の活動休止期間もありましたが、あの期間は「CHEMISTRYを続ける前提」で、一旦お互いにソロで経験を積んでいこう、という感覚だったのでしょうか。
川畑 まさにそうですね。「ソロでもやってみたい」という気持ちはお互いにずっとあったんですよ。そもそもオーディションも、ソロだと思っていたものが途中からデュオになったという経緯もありましたし。アルバムのなかでソロ曲があったりもしたけど、それぞれ一度じっくりとソロでも自分の形を作ってみたいなと。
だからこそ「活動休止」という表現で伝えるのは難しかったですね。ファンの方は、「もしかしたらこのままフェードアウトしちゃうんじゃないか…」とか考えるだろうし。なので15周年が見えてきた頃から活動再開を意識していって。「またCHEMISTRYに戻る」というのは、自分たちのなかでちゃんとしたかった部分でした。
―― また、初期のCHEMISTRY楽曲は作家さんが作詞作曲を手掛けていましたが、ご自身たちでも歌詞を書くようになった明確なタイミングというと?
堂珍 最初に俺と要で共作したのは、2003年ぐらいに書いた「Bright Lights」じゃないかな。デビューして2~3年経った頃ですかね。当時のバンドメンバーには、ムーンライダーズの白井良明さん、上々颱風の後藤まさるさん、ヒックスヴィルの真城めぐみさんとかがいて。彼らが、「ツアーのテーマになるようなことや、ふたりから出てくる言葉も聞いてみたい」と言ってくれたんです。それで自分たちの言葉でやってみたいなと。
で、ツアー中だったか、ツアーが終わってからか覚えてないけれど、曲を作ってもらってふたりで歌詞を書いたんですよ。そういうちょっと甘酸っぱいこともありました。それが最初ですね。
川畑 だからアルバム『One x One』の頃からですかね。当時、プロデューサーも変わって。そのタイミングで、自分たちも歌うだけじゃなく、もっと制作サイドに入ろうと。コンペのデモを100曲ぐらい聴いてそこから楽曲を選んだり。今思うと修行のような時間でした。ただ、俺はすべてを自分たちでやるのはあまり好きじゃなくて。最近よりその気持ちは強くなっている気がします。自分は歌い手として曲の良さを最大限に引き出したいというか。
堂珍 やっぱり気恥ずかしさみたいなものはありますよね。作詞も作曲も自分の内面ですから。何を考えているのかってところが思い切り出る。
川畑 そう。歌詞も手書きじゃ書けなかったし。自分の字だとリアルすぎて自分が受け入れられないんですよ。でもワードだとちょっと機械的になるから、「おぉ、歌詞っぽい」と思える(笑)。だからプロフェッショナルな方に入ってもらったほうが、よりよい作品ができるんじゃないかなと思うタイプなんですよね。
―― おふたりは歌詞面の「CHEMISTRYらしさ」とはどんなものだと思いますか?
川畑 なんだろうなぁ…。逆にプロデューサーの松尾潔さんがいつもおっしゃってくれる、「何を歌ってもケミになる」みたいな強みがあるのかなと思います。
堂珍 僕は自分を含めいろんなひとが当てはまるような、日常生活での葛藤というか、ちょっと下がりながらもまた進み続けるという歌詞が多い印象があります。あとラブソングだと、半永久的に歌えそうな言葉のイメージ。生々しかったり、キレキレだったりする感じではない気がしますね。逆に僕らの歌詞ってどんなイメージがありますか?
―― たとえばラブソングですと、曲によって物語は違いますがなんとなく共通する主人公像があるように感じます。優しすぎて、ちょっと自分が後ろに下がってしまうというか。
川畑 ああ、そうかもしれないな。遠慮がち。
堂珍 たしかに。その主人公そろそろやめてみるか(笑)。やっぱり基本、作詞家さんが僕らに当て書きをしてくださるじゃないですか。つまり、そういうふうに見てもらっている、ということなんだと思います。僕らふたりがどういう主人公の気持ちを歌ったら、より多くの方に届くのか、とかもあるでしょうし。そういうケミの土台があるからこそ、ソロでは「ちょっと変化球を投げてみようかな」とか「自分のイメージを壊してみようかな」とか挑戦もできるってことなんですよね。