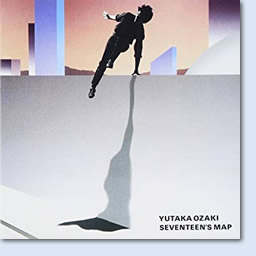2013年の12月で、デビュー30周年を迎える尾崎豊。彼は92年に26歳の若さで亡くなっているが、その人気はまったく衰えない。尾崎はいまも我々の心の中で生きているのだ。
僕が初めて彼に会ったのは、デビューする少し前のことだった。まさかその後、伝説的な人物になるなんて、当時は僕もふくめ誰も想像していなかった。デビューは1983年の12月だから、初めて会ったのは10月くらいだったのだろうか…。まず注目したのは、音楽より風貌だ。男が見てもドキッとするほどカッコいい奴だったのだ。ただし、当時の男性アーティストだと、人気絶頂はチェッカーズ。彼らと比較するなら、どちらかというと古風な美男子、という印象だった。
「歌なら作れますよ、いますぐだって」
初対面の挨拶を済ませた僕は、彼と一緒にエレベーターに乗り、上階にある会議室で話を聞くことになった。場所は市ヶ谷のソニーのビルで、壁面の色から“黒ビル”と通称されていた建物だ。今も鮮明に覚えているのは、時刻は夕暮れ時で、会議室の窓は開けられ、外堀通りを通る車の喧噪(けんそう)が室内にも聞こえていたことだ。そして部屋に入るなり、尾崎は上半身を窓から出して下をのぞき込み、一拍あった、僕に向かってこう言ったのだ。「歌なら作れますよ、いますぐだって」。
多分、彼は僕が訊きたいことを察してそんな言葉を口にしたのだろう。いや、僕自身の顔に「いつ、どんなふうにして歌を作るの?」という質問が“書いてあった”のかもしれない。メディアとの接触もまだ僅かだった筈なのに、既に通り一遍の質問には辟易(へきえき)としていたのだろうか…。
帰り道、尾崎の言った「いますぐだって」という言葉が、頭の中で何度もリピートしていた。尾崎が言いたかったことはなんだったのだろう。オレは「作為」からは歌を作ったりはしない、ということだったのか…。
「15の夜」というデビュー曲は衝撃だった
歌詞のことはあとで書くとして、まずは声だ。声量は豊かだし、歌の表現力(感情移入の仕方など)も深みがあった。歌謡曲の歌い手と比べても、問題なく歌が上手な部類だった。のちに十代の教祖と呼ばれた尾崎だが、そもそもこうしたオーソドックスな資質もあったわけだ。
詞の世界観に関しては、今まで一度も聴いたことのない新しさを感じた。しかもメジャー・デビューにも関わらず、プロの大人が手を加えた痕跡を感じられなかった。それほどリアルだった。それでいて稚拙ではなく、実際、大人にも耳にも充分響いた。
後から知ったことだが、実はプロデューサーの須藤晃は、何度も何度もダメ出しをしたそうだ。つまり実際には大人の手が加わっていた。しかしそれは、単に作品の純度を高める作業だったというわけで、このあたりのプロデュース・ワークは、今となっては驚嘆に値する。
「15の夜」は実話をもとに作られている。ファンには有名な話だろう。でも、実話だから説得力があるかというと、そう簡単な話ではない。校則に背き、学校での居場所がなくなり、仲間と家出を企てるという実際のアクションだけの歌なら、これほど名曲にはならなかった。単に日記の1ページから抜け出してきただけの歌に終わっていたことだろう。
まさに詩的とも言える心象風景の散りばめ方など、他にも多彩な要素が詰まった歌なのだ。見上げた空と対比される“やりばのない気持ちの扉”という表現や、自販機の“百円玉で買えるぬくもり”とか、これらのフレーズは言葉は平易だけれどとても冴えてる。
さらに尾崎の曲に対する言葉の乗せ方が斬新なのだ。ガチッとギアが入る部分と言葉が浮遊する部分との対比も効いている。何度聞いてもイイナと思うのは、“とにかくもう 学校や家には帰りたくない”の部分だろう。
ここのパートの大半はワン・コードであり、尾崎は特に旋律を意識せず、ふと気がつくと自分は呟いていた、という雰囲気を醸し出し、ただ、“帰りたくない”では一気にギヤを入れて声を張る。これ、突然閃いたのか、計算づくなのか…。何度聞いてもグッとくる。
ただ、この歌で最もメディアから繰り返し流されるのは、サビの“盗んだバイクで走り出す”のところだ。よくテレビなどで、反抗心を表現する際、その象徴であるかのようにここだけ使われたりもする。なので「15の夜」は反社会的な不良の歌、みたいなイメージにもなっている。しかし全体を聴くなら、そんなことはない。
“自由になれた気がした”
尾崎が望んでいるのが単なる反抗ではなくて、自身や仲間の成長であることは、この歌を“自由になれた気がした”という言葉で結んでいることでもわかる。あくまで“なれた気がした”のだ。最後にこれを持ってきたことで、この言葉は歌全体に作用する。バイクを盗んだのは犯罪。モチロン反省している、とまでは書かないが、彼が望んだのが破滅ではないことは充分に伝わってくる。
彼が世間に認められたのはデビュー直後ではない。「卒業」という歌を出した1985年だった。「15の夜」から約1年しか経ってないが、ふたつの歌を比較すると、格段の精神的な成長が見られる。“卒業”という言葉に込めた彼の意図を知ればそれが分かる。支配からの卒業を歌うこの歌だが、一番大事なのは己の中の敵からの卒業であることに、気づき始めている。
その後の彼は順風満帆とはほど遠いアーティスト生活となってしまった。徐々にコントロールを失っていく。この時期の尾崎は、高速で回転する駒であるかのように見えた。軸がまっすぐな回転ならまだいい。でもバランス失えば、己さえも弾き飛ばしてしまう。彼の葬儀には参列しなかった。家で彼のレコードを聴いていた。
僕が初めて彼に会ったのは、デビューする少し前のことだった。まさかその後、伝説的な人物になるなんて、当時は僕もふくめ誰も想像していなかった。デビューは1983年の12月だから、初めて会ったのは10月くらいだったのだろうか…。まず注目したのは、音楽より風貌だ。男が見てもドキッとするほどカッコいい奴だったのだ。ただし、当時の男性アーティストだと、人気絶頂はチェッカーズ。彼らと比較するなら、どちらかというと古風な美男子、という印象だった。
「歌なら作れますよ、いますぐだって」
初対面の挨拶を済ませた僕は、彼と一緒にエレベーターに乗り、上階にある会議室で話を聞くことになった。場所は市ヶ谷のソニーのビルで、壁面の色から“黒ビル”と通称されていた建物だ。今も鮮明に覚えているのは、時刻は夕暮れ時で、会議室の窓は開けられ、外堀通りを通る車の喧噪(けんそう)が室内にも聞こえていたことだ。そして部屋に入るなり、尾崎は上半身を窓から出して下をのぞき込み、一拍あった、僕に向かってこう言ったのだ。「歌なら作れますよ、いますぐだって」。
多分、彼は僕が訊きたいことを察してそんな言葉を口にしたのだろう。いや、僕自身の顔に「いつ、どんなふうにして歌を作るの?」という質問が“書いてあった”のかもしれない。メディアとの接触もまだ僅かだった筈なのに、既に通り一遍の質問には辟易(へきえき)としていたのだろうか…。
帰り道、尾崎の言った「いますぐだって」という言葉が、頭の中で何度もリピートしていた。尾崎が言いたかったことはなんだったのだろう。オレは「作為」からは歌を作ったりはしない、ということだったのか…。
「15の夜」というデビュー曲は衝撃だった
歌詞のことはあとで書くとして、まずは声だ。声量は豊かだし、歌の表現力(感情移入の仕方など)も深みがあった。歌謡曲の歌い手と比べても、問題なく歌が上手な部類だった。のちに十代の教祖と呼ばれた尾崎だが、そもそもこうしたオーソドックスな資質もあったわけだ。
詞の世界観に関しては、今まで一度も聴いたことのない新しさを感じた。しかもメジャー・デビューにも関わらず、プロの大人が手を加えた痕跡を感じられなかった。それほどリアルだった。それでいて稚拙ではなく、実際、大人にも耳にも充分響いた。
後から知ったことだが、実はプロデューサーの須藤晃は、何度も何度もダメ出しをしたそうだ。つまり実際には大人の手が加わっていた。しかしそれは、単に作品の純度を高める作業だったというわけで、このあたりのプロデュース・ワークは、今となっては驚嘆に値する。
「15の夜」は実話をもとに作られている。ファンには有名な話だろう。でも、実話だから説得力があるかというと、そう簡単な話ではない。校則に背き、学校での居場所がなくなり、仲間と家出を企てるという実際のアクションだけの歌なら、これほど名曲にはならなかった。単に日記の1ページから抜け出してきただけの歌に終わっていたことだろう。
まさに詩的とも言える心象風景の散りばめ方など、他にも多彩な要素が詰まった歌なのだ。見上げた空と対比される“やりばのない気持ちの扉”という表現や、自販機の“百円玉で買えるぬくもり”とか、これらのフレーズは言葉は平易だけれどとても冴えてる。
さらに尾崎の曲に対する言葉の乗せ方が斬新なのだ。ガチッとギアが入る部分と言葉が浮遊する部分との対比も効いている。何度聞いてもイイナと思うのは、“とにかくもう 学校や家には帰りたくない”の部分だろう。
ここのパートの大半はワン・コードであり、尾崎は特に旋律を意識せず、ふと気がつくと自分は呟いていた、という雰囲気を醸し出し、ただ、“帰りたくない”では一気にギヤを入れて声を張る。これ、突然閃いたのか、計算づくなのか…。何度聞いてもグッとくる。
ただ、この歌で最もメディアから繰り返し流されるのは、サビの“盗んだバイクで走り出す”のところだ。よくテレビなどで、反抗心を表現する際、その象徴であるかのようにここだけ使われたりもする。なので「15の夜」は反社会的な不良の歌、みたいなイメージにもなっている。しかし全体を聴くなら、そんなことはない。
“自由になれた気がした”
尾崎が望んでいるのが単なる反抗ではなくて、自身や仲間の成長であることは、この歌を“自由になれた気がした”という言葉で結んでいることでもわかる。あくまで“なれた気がした”のだ。最後にこれを持ってきたことで、この言葉は歌全体に作用する。バイクを盗んだのは犯罪。モチロン反省している、とまでは書かないが、彼が望んだのが破滅ではないことは充分に伝わってくる。
彼が世間に認められたのはデビュー直後ではない。「卒業」という歌を出した1985年だった。「15の夜」から約1年しか経ってないが、ふたつの歌を比較すると、格段の精神的な成長が見られる。“卒業”という言葉に込めた彼の意図を知ればそれが分かる。支配からの卒業を歌うこの歌だが、一番大事なのは己の中の敵からの卒業であることに、気づき始めている。
その後の彼は順風満帆とはほど遠いアーティスト生活となってしまった。徐々にコントロールを失っていく。この時期の尾崎は、高速で回転する駒であるかのように見えた。軸がまっすぐな回転ならまだいい。でもバランス失えば、己さえも弾き飛ばしてしまう。彼の葬儀には参列しなかった。家で彼のレコードを聴いていた。
小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number
プロフィール 小貫 信昭
(おぬきのぶあき)
1957年東京は目黒、柿ノ木坂に生まれる。音楽評論家。
1980年、『ミュージック・マガジン』を皮切りに音楽について文章を書き始め、音楽評論
家として30年のキャリアを持つ。アーティスト関連書籍に小田和正、槇原敬之、
Mr.Childrenなどのものがあり、また、J-POP歌詞を分析した「歌のなかの言葉の魔法」、
自らピアノに挑戦した『45歳、ピアノ・レッスン!-実践レポート僕の「ワルツ・フォー
・デビイ」が弾けるまで』を発表。
1957年東京は目黒、柿ノ木坂に生まれる。音楽評論家。
1980年、『ミュージック・マガジン』を皮切りに音楽について文章を書き始め、音楽評論
家として30年のキャリアを持つ。アーティスト関連書籍に小田和正、槇原敬之、
Mr.Childrenなどのものがあり、また、J-POP歌詞を分析した「歌のなかの言葉の魔法」、
自らピアノに挑戦した『45歳、ピアノ・レッスン!-実践レポート僕の「ワルツ・フォー
・デビイ」が弾けるまで』を発表。