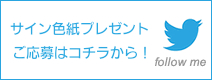―― 今作のアルバムタイトル『カフネ』は、どのようにたどりついた言葉でしょうか。
『カフネ』とはポルトガル語で、愛しいひとや大切なひとの髪に指を通して、優しくといたり、撫でたりする様子を意味する言葉です。そうした行為によって、相手を落ち着かせたり、眠りにつかせたりする。そんな愛情表現が込められているんですね。
今作には、かなり前に作った楽曲も多く収録されていますが、8曲目「ゆう」だけは、アルバムのテーマが見えてきてから新たに書き下ろした楽曲で。その「ゆう」という最新曲を踏まえて、改めてアルバム全体を見通したとき、浮かび上がってきたのが、“自分と他者との距離の近さ”や“感じる体温”、“その場の空気感”といったものでした。そういうニュアンスを表す言葉として、『カフネ』というタイトルにたどり着きました。
―― 今作のリード曲であり、最新曲となる「ゆう」はどんなきっかけから生まれたのですか?
やはり言葉の本質を考えていたところが始まりですね。この曲の場合、「“幸せ”とは?」ということでした。僕はその答えを明確にわかっていなくて。たとえば、「音楽で生活できるようになりたい」とか、「いろんなひとに歌を聴いてほしい」とか、ずっと望んでいた。その時期に比べると今は、メジャーデビューもさせてもらって、多くのひとに知ってもらって、満たされているはずなんです。でも、「まだもっと…」と尽きない欲望もある。
だからこそ、「幸せのゴールって何だ? もしかして終わりのないものではないか?」とある種の恐怖も感じるようになっていたんです。そんななか、「え、そんなことで?」と思うようなことで、「幸せ」と言っているひとがいて。そのときにまた気づきを得たというか、救われました。幸せって、もっと狭いところ、小さいところにいくつも転がっていて。それをちゃんと捉えて拾い上げられる“自分の心の在り方”が大事なのか、と。
―― とはいえ「ゆう」はただ幸せだけを描いたラブソングではありませんね。<君>は<もう生けてはいけないような 残酷な悲劇の中も 終わりを選ばずに 生きて>きたひとです。
そうなんですよ。誰しも人生のなかでいろんなツラいことってあるじゃないですか。そのなかで日々の幸せに気づくことができる素晴らしさを表現したかったんです。絶望のなかにいると、「自分ばかりが不幸だ」とか、「自分は恵まれない人生だった」とか、結論づけてしまうひともいると思います。だけどそうじゃなくて、「でも今日はこんなことで笑えたな」とか「でも明日はここに行くし」とか、日常に幸せの種を見つけられたらなと。
―― また、<君が 何年かけても消せない 僕には触れない過去が 何度 目覚めても 寝かしつけといてあげるから>というフレーズには愛が満ちていますね。きっと<僕>も、誰かの過去は、他者が薄めたり消したりはできないことを知っているからこそ、<寝かしつけといてあげる>という表現をしているのかなと。
まさに自分がそうなのですが、つらい出来事を含め、踏んできた過去をなかったことにはできなくて。それを思い出すトリガーは日常のなかにいくつもある。どうしても忘れることはできない。それでも、何度でも「大丈夫だよ」と言ってくれるひとがそばにいてくれれば、生きてゆける気がするんです。
自分も誰かにとって、そういう存在でありたい。思い出したくないことを、ふと思い出してしまって苦しいとき、懲りずに寝かしつけてあげられる音楽を作り続けたい。そんな気持ちが「ゆう」には込められていて、さらに『カフネ』というアルバムタイトルに集約されていくなと思いますね。
―― アルバムの入口となる「君想う夜」は、センチミリメンタル公式TikTokを拝見したところ、2020年にはもう披露されている楽曲なのですね。
作った時期でいうと2015年ぐらいなので、もう10年ほど前からあった曲ですね。前作『やさしい刃物』では、1コーラスしかない短い曲「suddenly」を1曲目としてプロローグ的な立ち位置にしていて。そこを引き継ぎたかったのと、歌詞のメッセージも『カフネ』にふさわしいというところで、今作は「君想う夜」を1曲目に持ってきました。シンプルで余白の多い歌だと思います。
―― <君>を想いながら、<一人でうずくまって>いる状態と、<一人で漂う>状態のどちらも描かれているのが印象的です。
誰かを大事に思っているときの不思議だと思うんですけど、狭いところに閉じ込められている感覚と、広いところをさまよっている感覚、どちらもあるんですよ。さらに、「出会えてよかった」、「出会わなければよかった」、 「愛おしい」、「でも寂しい」、いろんな感情がずっと頭のなかをぐるぐるしている。その常に変化し続けている様子を、言葉でも音でも表現したくて作った曲ですね。
―― 少し話が逸れますが、「君想う夜」はTikTokの投稿にとくに海外の方からのコメントがものすごく多くて驚きました。
そうなんですよ。海外はライブでも行かせていただくことが多くて。僕は勝手に、海外の方々はなんとなくサウンド感や曲のニュアンスで楽しんでくれているものだと思い込んでいたんです。でも、よくお話を聞いてみると、「歌詞に救われました」、「歌詞に人生を支えてもらいました」と言ってくださることが多くて。ちゃんと言葉が届くものなんだと僕も驚きでしたし、喜びを感じています。
―― 温詞さんの歌詞に対する真摯な姿勢が、海外の方にも伝わっているのだと思います。
とくにこういうシンプルな歌を書くときほど、難しさと戦っていますね。中身のない言葉と紙一重なので。先ほどもお話しましたが、僕は遠回りな表現ばかり大事にしている時期があって。その当時、ものをズバッと言う音楽仲間に、「温詞くんの歌詞って、いい感じの綺麗っぽいことを言っているだけだよね」って言われたんです。
僕はそれがとても悔しくて。自分のなかでは、かけがえのない思いや伝えたいメッセージがある。それをわかりやすく表面化してないだけなのに、気づいてもらえないんだという寂しさ、苛立ちを抱きました。実は「君想う夜」は、そう言われたことに対するあてつけのように書き始めた曲だったんですよ。
―― 「それならいったんシンプルに書いてみよう」と。
はい。すると、その曲を聴いたそいつが「めっちゃいいじゃん」と言うので、「結局、わかりやすい単語を使えばいいってことかよ」と最初は思いました。
でも、自分が大切なひとと出会ったり、誰かを愛おしいと思ったりという経験をした上で、改めて「君想う夜」を歌ってみたとき、聴いてみたとき、歌詞を読んでみたとき、「ああ、たしかにこれがすべてかもしれない。会いたいときには“会いたい”と言えばいいんだ」と気づかされて。そこがまた悔しかったんですけど(笑)。シンプルな言葉だからこそ、届くものがあるんだなという学びは、僕にとって大きなものでした。
―― アルバムのラストを飾る「愛の証明」もまた、ストレートな伝え方で、一貫して<君>を想い続けているラブソングですね。
「愛の証明」は、歌詞にものすごく悩んで、なかなか納得できず、書き上げるまでに1年ほどかかりました。最初はとにかく、「自分の痛みや悲しみ、ツラさをわかってほしい」という思いだけで作ろうとしていたんです。でも、それをどう歌に落とし込めばいいかわからなくて、だらだらと自分の気持ちを述べるだけで、それこそストレートの意味をはき違えて言葉が幼稚になってしまって。うまくまとめられず、泣く泣く1回ボツにしました。
ただそれが、時間をかけてかみ砕いてみたとき、腑に落ちた瞬間があって。自分を大きく捉えられたというか、自分の感情を肯定してあげられる言葉が見つかった。そこから、すべてを組みなおして作り上げることができたんですよね。
―― そのきっかけとなった言葉は何だったのでしょう。
冒頭の<君とさよならをしたあの時 きっと僕は死んでしまって それからは僕によく似ている 知らない誰かとして生きてる>というフレーズですね。実際に自分自身が、「ああ、そうか、あのとき僕は死んだのか」って本当にふと腑に落ちたというか。そう思うことができたとき、「愛の証明」を書き進められたんです。
もちろん自分の人生は続いていて。大切なひとと過ごした頃の自分とは、違う道を歩んでいる。もうそのひとと結ばれることもない。だけど、そのひとの影響は明確に受けているのに、平気な顔で違う道を生きている自分のことをずっと肯定してあげられませんでした。
そんなとき、冒頭のフレーズを思うことができて、ちょっと楽になったんですよね。「もう違う人生になったのだからしょうがないか。あのひとが横にいない、第2の人生なんだ」って。すると、客観的に当時の自分の思いを言葉にすることができて。一気にバーッと書くことができました。この曲はまさに“キモい”歌だなと思います。
―― 別れてからの“愛の証明”ってなかなかないですよね。
こんな気持ち悪いことを現実で言うのは許されないでしょうね(笑)。かといって、「またよりを戻したい」とかではなく。そのひとから受けた影響、そのひとがいたからこそのご縁や生まれた音楽、それらを丸ごと肯定したかったんです。だから、たとえ別れていても<君を愛してるよ>と思うことを許してあげたい。意外とここまで真っ直ぐに愛情を歌ってあげる失恋ソングってない気がします。
僕は常に振り返ってしまうタイプの人間で。未練がましいし、パッと生まれ変わる潔さもないし、今だけを生きられない。でもきっと誰しもそういう部分はどこかにあって。「次の恋愛に行こう!」というポジティブさも美しいけれど、心のドロッと情けない部分を、胸を張って表現することが僕の使命なのかなって思うんですよね。音楽という形に残すことで、あのひとのなかにも作品として残ってもらえるんじゃないかという願望もあります。
―― 今作に収録されている「東京特許許可局」や「ミラーソング」といった悲しいラブソングも、「愛の証明」によって救われる気がします。
たしかに、失恋ソングの総括みたいな面がありますね。自分にとってこの“愛”は、形を変えながらも、ずーっと引き連れて生きてゆくもの。その愛に含まれている悲しみも何もかも、丸ごと肯定してあげられる優しさと強さとキモさを、ギュッとまとめたのが「愛の証明」ですね。この歌が『カフネ』というアルバムのエンドロール的なポジションを担ってくれたことも、よかったなと思います。